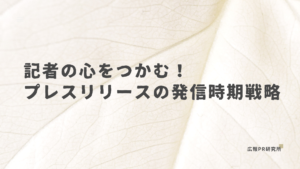震災後の広報:共感するPR活動
2024年1月1日、16時10分ころに震度7の「令和6年能登半島地震」が発生しました。震源地は石川県能登地方で津波も発生するなど大きな被害が出ています。
被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。まだ、被害状況も確認できていない中ではありますが、一日も早い復旧と皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。
日本は、阪神淡路大震災以降、震度7クラスの巨大地震が複数回発生するなど自然災害が非常に多い地域になっています。
そのため、災害時の広報対応が特に重要視されています。
そこで、今回は震災直後~数か月後までの広報対応の方法についてご紹介します。
災害時は細心の注意をした「共感」する広報活動
地震や火災による建物の倒壊や津波、水害などが引き起こす人的被害や避難指示などは、国や自治体が対応するものです。ただし、企業が事故や事件を起こし、それが二次災害を引き起こす場合は、プレゼンスが失われてしまう恐れがあります。
そうした中で、震災後は「共感」した広報活動が重要です。
被災者がいる中では、細心の注意をして広報活動をすることで企業の好感度を向上させましょう。
震災直後の広報活動
震災直後には、一般的にはビジネスやサービスなどのプレスリリースや記者発表は控えます。
震災直後は、被害を受けた状況から復興前に知名度を向上させるために、大きなビジネスチャンスになります。しかしながら、被災者からは「ビジネスのためだけに情報発信している企業」と悪い印象を受ける傾向にあります。
良いビジネスであったとしても、今はSNSもあるため、心象を悪くするような情報発信であればクレームが拡販されるリスクにもなる恐れがあります。
そのため、震災直後に対外的に広報として発信すべきは、復興支援や募金などの社会貢献活動に居できるプレスリリースが良いでしょう。
なお、東日本大震災時には、PRイベントなどを予定していた企業では被災者の感情を考慮し、中止・延期とする“自粛ラッシュ”も起きました。
どうしてもサービスを発信したいとき
社内の指示でビジネスやサービスを被災者向けに展開する旨で情報発信したいと入ることはあると思います。
そういうときには、「リーク」を上手に利用しましょう。
「リーク」とは、1社の記者に情報を伝えることです。記者にとって独自情報と扱えるため、記事になりやすいメリットがあります。
また、「リーク」だと第三者による記事となり、記者も企業側を配慮してくれるため、読者はプレスリリースと比較して悪い印象は与えにくくなります。
プレスリリースをすると印象を悪くする際には、「リーク」を上手につかうことを検討するとよいでしょう。
お見舞い文の掲出
広報の業務では、お見舞い文のホームページへの掲出も重要になります。
被災者へのお見舞いを企業として表明することで、直接ステークホルダーからの印象が向上することに繋げることが期待できます。
そのため、災害を想定して事前に災害のお見舞い文の例文を作成するなど、メディア対応の準備を進めておくとよいでしょう。
災害のお見舞い(例)
この度の〇〇〇〇により被災された皆様、ならびにそのご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
被災された皆様の生活が1日も早く平穏に復することをお祈り申し上げます。
震災直後は社内広報を主軸に
災害直後に大切なことは、社内外への広報対応を整理しておくことです。
特に社員・従業員とその家族の安全を確保するための社内向け広報活動が求められます。これには、社員の連絡先情報を含む連絡網の整備や、事前に連絡手順を整備することが含まれます。
災害時にはイントラネットに緊急連絡ページを開設し、外部の伝言ダイヤルを活用し、連絡網を通じて自社の被害状況を社員に周知するなどの作業を検討するとよいでしょう。
こうした業務を広報が担うことで、効果的かつ的確な対応が可能となります。
サービス展開などの情報発信は数か月後に
これまでの震災では、数か月(2~3か月)が経過すると被災者の悲痛な状況を伝える報道が減少します。
それとともに、復旧・復興に向けた取り組みが報道され、震災関連の特集が組まれ、復旧復興の様子が報道されることとなります。
当然、震災後の情報発信になるため細心の注意が必要になりますが、そうしたタイミングがビジネス関連の発信ができるチャンスになります。
例えば、モンテローザグループが展開する企業である株式会社モンテローザは、「食べて飲んで復興支援するぞ」キャンペーンを実施しています。このキャンペーンでは、東北地方の名物や地酒を新たに販売し、対象商品1品につき10円を義援金として被災した地域の行政機関に寄付されます。モンテローザはこの取り組みにより、「ひるおび!」など複数のメディアにおいて「企業、消費者、被災者の三方にメリットがある活動」として報道されました。
そのほかにも、被災者限定の商品として一般の方よりも低下価格に販売するなどをする企業もあり、報道につながっています。
被災地への共感をしながら、情報発信することで批判を受けずに会社のプレゼンスを向上させていきましょう。
まとめ
これまでに説明した内容は被災地の状況次第で、広報が何をすべきかは変わってきます。
せっかくの良い事業活動が、被災者への配慮に欠けていたら批判につながってしまいます。
そのような状況になってしまったら、広報担当者がいる必要がありません。
そのため、随時現地の状況に関する報道を確認し、他社のプレスリリースや報道を確認して、ステークホルダーに共感されるような広報活動を進めていきましょう。
筆者プロフィール
10年以上の間、記者発表や取材対応、リリース作成などの社外広報を担当。これまでに100回以上の記者発表や1,000本以上のリリースを作成。震災時の広報対応も担当。自社だけでなく、グループ会社の広報業務も手掛けているため、大手企業から中小企業の情報発信を経験している。専門媒体や地方媒体から全国のニュースまで多方面での広報の企画立案と実施を行っている。